~建築目線で語る、サンガスタジアムの真の応援力とは~
こんにちは。「京魂フットボール日記」運営者のhishigaです。
滋賀県在住、建築会社に勤務しながら、週末は京都サンガF.C.の応援に情熱を注ぐ日々を過ごしています。
2004年、西京極スタジアムでの初観戦をきっかけに、以来20年以上。
サンガの苦しい時代も歓喜の昇格も見届けてきた私にとって、サッカー観戦は人生の一部です。
そんな私が最近強く感じるのは、「スタジアムそのものが、チームの一員である」ということ。
この記事では、建築業界で働く立場から、京都サンガのホーム「サンガスタジアム by KYOCERA」が、いかに応援の力を引き出す空間として設計されているかを、具体的に解説します。
スタジアムの“応援力”は構造から生まれる
私が初めてサンガスタジアムに足を運んだとき、まず驚いたのはピッチとの距離の近さ。
特にゴール裏から見る試合は、「自分もプレーの一部になったような感覚」にさせてくれます。
これは建築的には、スタンドの傾斜角度・高さ・距離感を綿密に設計した結果。
- スタンド傾斜が急めで、前列との視線被りがほぼない
- 距離はJリーグ基準でもかなり近接(約7.5m)
- 屋根の張り出しが音の反響を生み、一体感を演出
つまりこのスタジアム、物理的構造が「応援しやすい・声が届く・臨場感がある」空間づくりを支えているんです。
応援の熱を“増幅させる”設計
建築の世界では、「空間が人の行動を導く」とよく言います。
サンガスタジアムには、まさにその考えが活きている部分があります。
たとえば:
- ゴール裏席は1層構造で縦に声が届きやすい設計 → コールが伝播しやすく、熱量の軸をつくる
- メインスタンドの屋根は応援の“反響板” → 拍手・声援がピッチ側に返ってくるように響く
- **座席の配置が“ぎゅっと集まる感覚”**を生む → サポーター同士の距離感が近く、自然と仲間意識が生まれる

これは単なる観客席じゃない。
ファンの熱を“ひとつの波”にして選手へ届ける、“応援装置”としての設計がされていると感じます。
試合外の空気もデザインされている
スタジアムは試合中だけでなく、前後の空気が“観戦体験の質”を決定づけます。
亀岡駅からスタジアムまでのペデストリアンデッキは、アクセス面だけでなく、

- スロープ配置の緩やかさ
- 通路幅と照明演出
- 紫を基調とした配色で“サンガ感”をじわじわと演出
まさに、「街とスタジアムを繋ぐ、空間的なドラマ」が生まれる場所。
私は帰り道にライトアップされたスタジアムを見ながら、「今日もこの空間に包まれて応援できたな」と心がほっとするのを感じます。
サンガスタジアムは“応援のホーム”として設計されている
建築会社で働く私が強く共感するのは、このスタジアムが**“汎用施設”ではなく、“京都サンガ専用”として最適化されている点**です。
- ピッチとの距離と高さ
- 応援を妨げない視認性
- 通路・ゲート・照明の演出設計
- 雨でも応援を楽しめる屋根の張り出しと動線計画(※一部通路は開放構造で雨対策も要注意)
つまりこれは、“建築的にも京都サンガの一員”と言っても過言ではありません。
選手を支える声、ファンの感情、スタジアムのつくる空気が融合した場所。それが、サンガスタジアムなのです。
まとめ|スタジアムは、チームを支える“無言のパートナー”
京都サンガの試合を20年近く見守ってきた私にとって、サンガスタジアムはただの会場ではありません。
応援の声を包み込み、
高揚感を生み、
心がひとつになる場所。
建築は「モノをつくる仕事」でもあり、「空気をつくる仕事」でもあります。
サンガスタジアムはまさに、“応援の空気”を生み出す建築の力が活かされたスタジアム。
だから私は、
サンガスタジアムは、もうひとつのチーム。
声なき応援者なのだと思っています。


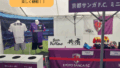
コメント